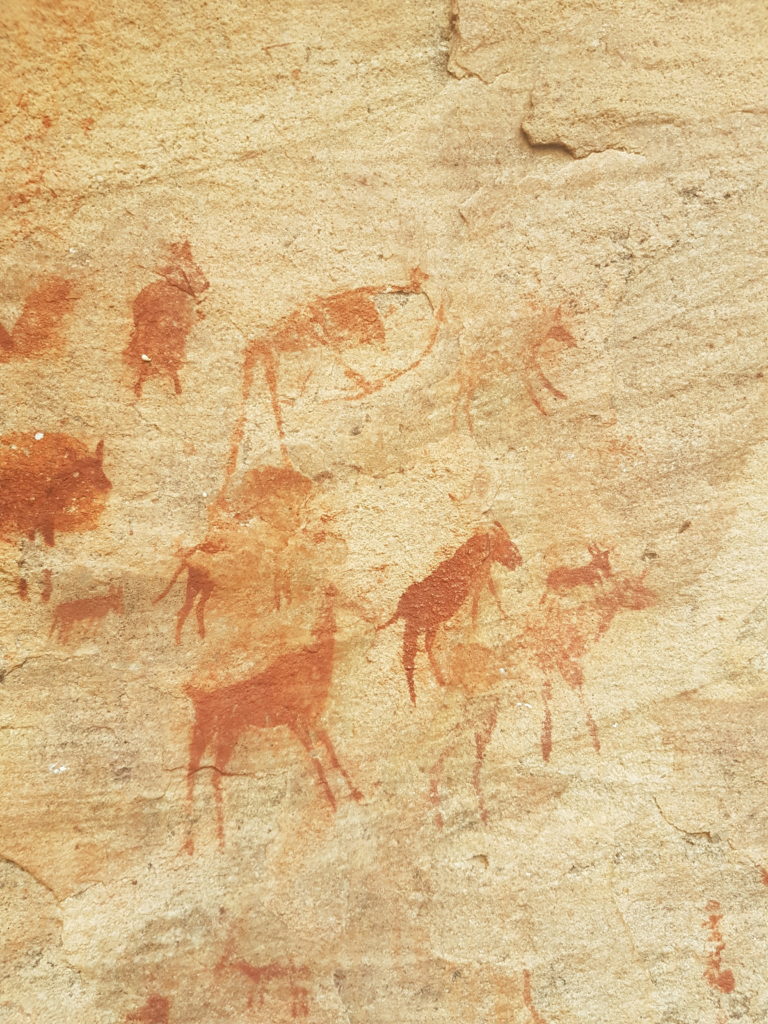※過去の動画や画像がありますが、現在は違う状況です。 住んでいる場所 ロビはブルキナファソ南東・コートジボワール北東 Art and life in Africa map ざっくりヒストリー ロビは現在のガーナから1770年頃にブルキナファソ南部に移住し、その多くは国境を越えて現代のコートジボワール北東部に移り、また一部はコートジボワールからブルキナファソ南部に戻ってきたりしました。 移動の理由の一つには、植民地時代の奴隷狩りから逃れる為であったといわれます。 かつて、ロビは自分たちのコミュニティ外からの政治的権力に抵抗した人々として有名でした。ロビの村はそれぞれ基本的に独立しており、ロビ全体での政治的なまとまりはありませんが、フランスの植民地化には強い抵抗を示してきたといわれます。 相手は銃を持っていたと思いますが、弓矢で勇敢に戦ったともいわれます。 生活 ロビは主に、キビ、モロコシ、トウモロコシを耕作する農業を営んでいます。 男性は通常、畑の開拓と植栽の準備を担当し、女性は種蒔きと収穫のほとんどを行います。また、農業の合間に男性も女性も手工芸品を作り、地元の市場で販売します。家畜や牛の飼育も行い、その一部は結婚の持参金や罰金の支払い、信仰の供物として使用されたりします。 ロビは古来より狩猟中心の生活を続けていましたが、銃の普及により獲物が減少し農業中心の生活に移行してきたといわれます。 Society of African Missions の動画リンク 1950年頃の様子のようで、現代の様子ではありません。少し上から目線も感じますが、当時の様子、生活の道具、後半に葬儀の様子など見る事が出来ます。 コミュニティー ロビの村は点在して広がっており、しばしば他の民族エリアと混ざり合っています。きっちりと地理的に区別することは難しいです。また、個々の村に存在するティラ(神の使者)同士の提携により、地理的に離れている村でも同じコミュニティーとしてとらえる事もあります。 宗教的な占い師はコミュニティの長として認識され、色々な決定事項・道徳の規範など、村の住民は基本的にそれに従って生活していきます。各村は基本的に独立しているので、ある村では禁止されているものが別の村では大丈夫だったりと、村ごとのルールには特徴があります。 ■ロビの村に旅行に行かれた方の、ブログ記事を見つけました!その時、村の方から聞いたロビの説明をまとめた記事がとても良いのでリンクをいれます。これだけでなく、アフリカの色々な記事がとても良くまとまっていて、素晴らしい!最近のロビの様子も旅行記から伺えます! →ブログ:アフリカに「おもいやり」のロビの基本情報ページ →ブログ:アフリカに「おもいやり」のロビの村旅行記①ページ →ブログ:アフリカに「おもいやり」のロビの村旅行記②ページ 四角底のストローバスケットはこの地域の形だったのか! 神話・精神世界 ロビはかつて彼らと神と一緒に理想の楽園に住んでいて、何も望んでいないと信じていました。しかし、人々の数が増加し始めると男性は女性をめぐって互いに戦い始め、その結果、神は人々に背を向けてしまいました。 しかし、神は人々が完全にいなくなることを望まなかったので、人々を見守る使者としてティラ(thila)を人々の世界に送りました。ティラは自分のメッセージ・要求・禁止事項を、占い師を通して人々に伝えます。 また、ティラの世界では男性の上に多数の自然霊が存在するといわれます。ロビには自然霊とティラを難なく区別できるといいますが、これは外部の人には分かりずらい事でもあります。 作品 (木彫・ブロンズ・陶芸・建物・音楽など) ■木彫 ロビは毎日使用される道具から、宗教的な理想を具現化する人物まで、木彫品を作ります。 その一つに神話に基づいた精神世界を現す「バティバ Bateba 」と呼ばれる木彫の人形があります。 ロビの人々の精神的世界観には、創造神の次に「ティラthila」 と呼ばれる目に見えない超自然の精霊が存在しています。「バティバ 」は「ティラ」の助手と考えられ、祭壇に祀られた瞬間から命を授かり、人間を妖怪や病から守り、富や健康、豊作、結婚、出産などの幸福をもたらすといわれています。 「バティバ」は様々な種類があります。 動物は基本的には「バティバ」の助手役で、鳥、ガゼル、キリン、カバ、ゾウやカメレオンなどがあります。造形はシンプルですが、この動物には生命が吹き込まれたような存在感があります。 また、「バティバ」は「ティラ thila」(超自然の精霊) の祭壇に配置され、互いに通信し、魔物と戦うことができる生物として認識されています。 ロビの祭壇は家の奥の暗い場所に大体ありますが、「バディバ」は時々魂だけ外に外でお出かけするそうです。(リフレッシュですかね?) 神と木彫と人の関係をまとめると、大体こんな感じでしょうか? 「神」 ↓ 超自然霊「ティラ」(神の使い) ↓↑ 交信 ←占い師 間を取り持つ 祭壇に置かれた木彫り「バディバ」 → 時々、祭壇の外に外出する ↓ ←占い師 間を取り持つ ロビの人々 富や健康、豊作、結婚、出産などの幸福をもたらす ■多種多様な護符 妖怪や病気、攻めてくる敵から身を守る為の護符 富や健康、豊作、結婚、出産などの幸福をもたらすもの ■美しい建物やインテリア ■音楽 reference:The University of Iowa Stanley Museum of Art , Art &Life in Africa